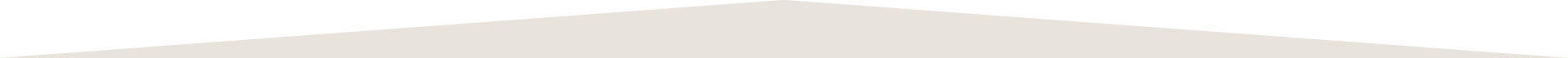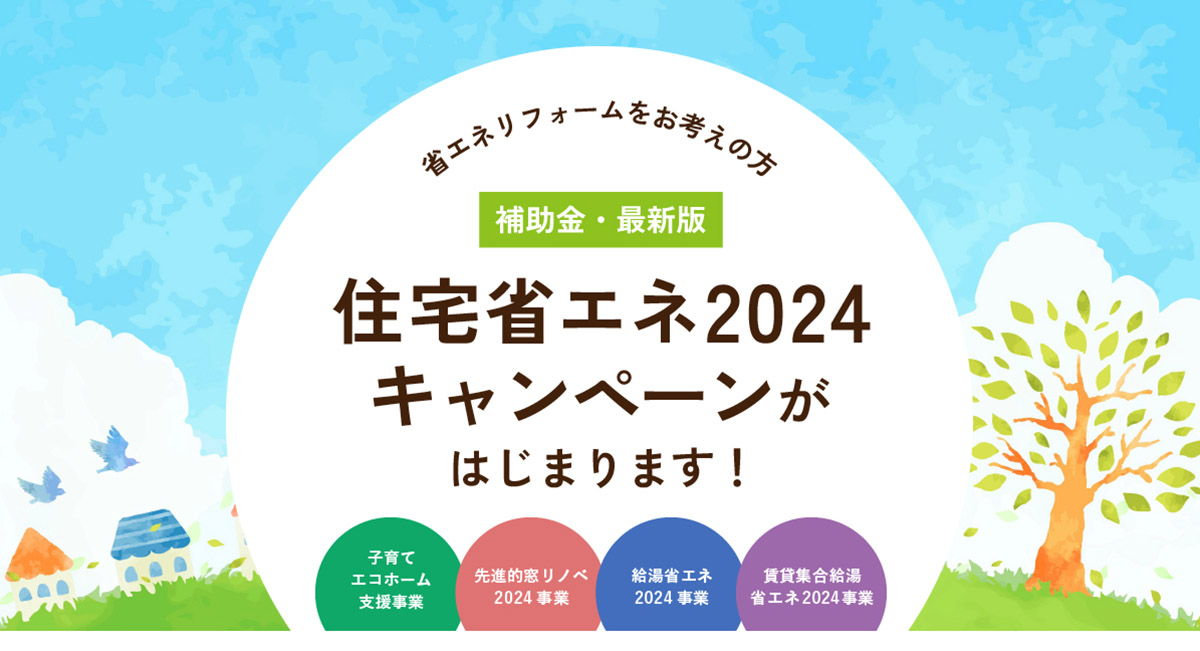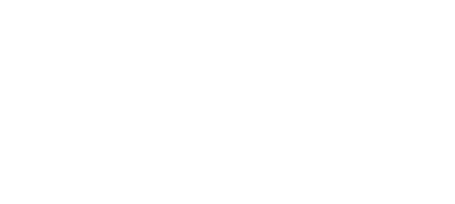日本では夏になると湿度が高くなり、蒸し暑さが増します。昔から日本の家づくりでは、『木』は欠かせない素材です。家具や床材、建具などさまざまな箇所で使われています。
しかし、木は「呼吸する素材」と言われるように、湿気と密接な関係があるのをご存知ですか? だからこそ、木を使った家づくりやリフォームをするなら、湿気との付き合い方はとても大切です。
今回は、木と湿気の関係や、木をもっと長持ちさせるためのポイント、さらに最近注目されている「高気密・高断熱リフォーム」についても解説します。
木は湿気を吸ったり吐いたりする?

木の繊維の中には細かい空気の通り道があり、空気中の水分(湿気)を吸ったり、吐いたりしてくれます。これを「調湿性」といいます。
湿度が高いときには余分な水分を吸い、乾燥しているときには吐き出してくれるため、周囲の湿度をある程度調整し、室内環境を快適に保つのに役立っています。
ただし湿気を吸いすぎると、木が膨張・変形したり、カビや腐朽菌の繁殖を招くこともあります。逆に乾燥が進むと収縮や割れの原因にもなるため注意が必要です。
木の種類でも、湿気への強さは違う

木の種類によって、湿気に対する耐性も異なります。
- ヒノキ:湿気に強く、調湿性に優れます。またヒノキに含まれる天然成分に防カビ・抗菌作用があるためカビにくいです。湿気の多い浴室にも使用されます。
- スギ:軽くて加工しやすく、繊維の間に空気を多く含む構造のため、吸湿性が高いです。湿気を吸いすぎると反りや割れに繋がりやすいので、適切な換気や仕上げ処理が大切です。
- ナラ(オーク):硬くて密度が高いため、湿気による伸縮が起こりにくく、耐久性に優れます。家具やフローリングにも適しています。
- チーク:天然の油分を多く含むため、耐水性が高く防虫性にも優れています。湿気の多い環境でも腐りにくいので、船舶のデッキ材やガーデン家具にも多く使われています。
- ウォールナット:非常に耐久性が高く、家具や内装材でよく使われています。チークほどの耐水性はなく、湿度に対する安定性は中程度のため、室内の適切な湿度管理が必要です。
木を長持ちさせるためには

木を長持ちさせるには、湿気をためない・吸い込みすぎない・乾燥しすぎない環境をつくることが大切です。
● 部屋の風通しをよくする
● 除湿機や換気で湿度をコントロール(目安は湿度40〜60%)
● 家具は壁や床にくっつけず、少しすき間をあけて置く
● 水や汚れはすぐにふき取る
● 定期的に木にオイルやワックスをぬってケア
室内の湿度環境を整えて、適切な手入れをする事で、カビたり変形したりしにくくなり、木を長く美しく保つ事ができます。
もっと快適にするなら「高気密・高断熱リフォーム」

木の良さを活かすには、実は「家そのものの性能を上げる」のも、とても大切です。そこで最近注目されているのが、高気密・高断熱の家づくりです。
高気密・高断熱とは、簡単にいうと「外の暑さ寒さを中に伝えにくくし、家のすき間を減らして空気の出入りもコントロールする」ということです。これをリフォームで取り入れると、色々なメリットがあります。
- 湿度の変化が少なくなるので、木が反りにくい・傷みにくい
- 結露が減って、カビや腐食を防げる
- 冷暖房の効きがよくなって、電気代の節約に
- 年中快適な温度と湿度をキープできる
つまり、木を長持ちさせる環境をつくるためには、高気密・高断熱リフォームがとても相性が良いんです。
どんなリフォームで実現できるの?
実際にどんなリフォームができるの?という方のために、いくつか例を挙げてみます。
- 壁や床、天井に断熱材を追加・施工性・断熱性の高い断熱材を選ぶ
→ 室内と外の温度差を小さくし、湿気をシャットアウト - 窓を二重サッシや気密性の高い樹脂サッシに交換
→ 結露の発生を軽減 - 換気システムを取り入れる
→ 24時間ゆるやかに空気を入れ替えて、常にクリーンな室内に。
木のある暮らしは、環境づくりから

木のぬくもりって、ホッと心が落ち着きますよね。その心地よさを長く楽しむには、「湿気との上手なつきあい方」が欠かせません。
そしてそのポイントのひとつとなるのが、家そのものの性能です。高気密・高断熱のリフォームで、木がもっと長持ちする住まいになります。
「これから無垢材のフローリングにしたい」「木を使ったあたたかみのある家にしたい」そんな方は、ぜひ木+湿気対策+高性能リフォームを意識して住まいづくりをしてみてください🏠
ZERO×STYLEではリフォーム・リノベーションのこと・住まいづくりに役立つ記事を随時更新しています。
興味のある方はぜひチェックしてみてください。(^^)/
ZERO×STYLE ブログ記事:https://housing-staff-2nd.jp/zerostyle/blog/